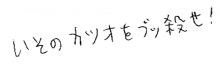
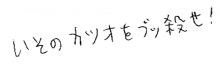 |
昔々あるところにくず川が流れていました。汚いからくず川と言うのではなく、くずの花が咲くのでくず川と言うのですが、実際汚かったし、別にくずの花なんか咲いてもいませんでした。そんなくず川には、名前のない橋が幾つも幾つも架かっていて、町の皆は毎日何かしらの用事で橋を渡っていました。くず川のすぐ傍にある僕の家の前にも、名前のない橋が架かっていて、その橋は登校班の集合場所となっていたので、僕等は毎朝その橋の前に集まり、毎朝その橋を渡り、小学校に登校していました。ちなみに通学路には、ボブとあだ名された浮浪者がいて、僕等は毎朝ボブに石を投げつけるのを日課としていたので、いつも遅刻ギリギリでした。でも、バカでかい石がボブの頭に命中して、血だらけになったボブが学校まで追いかけて来た朝は、全力疾走で登校したので、遅刻などしませんでした。が、放送で呼び出され、血だらけにならない程度にピンタされました。そんなある日の朝、いつもの様に登校班の皆が集まると、血だらけのモリを持ったボブが、橋の下からノソノソと出て来ました。ボブは僕等を見て、ニヤッとしました。ボブの左手にはビニール袋が持たれていて、その中には血だらけの鯉が入っていました。その鯉は町のお偉いさんが、川を美しくしようと放流した鯉でした。登校班の班長がボブに、「その鯉どうしたの?」と聞くと、ボブは、「食うんだよ」と言いました。鯉はビニール袋の真っ赤な血の中で、口をパクパクとさせていて、目を見開いていました。僕等はボブの歩いていく後ろ姿を、ただ見つめるだけで、石は投げつけませんでした。
そんなある日の夕方、いつもの橋の上に、小山ゆう子が立っていました。ゆう子ちゃんはちょっと太めの女の子で、家が遠いので、大概の場合一人で登下校していました。小学校に上がる前くらいまでは、隣に住んでいたので、僕は将来ゆう子ちゃんと結婚するんだ、と決めつけていました。ゆう子ちゃんは、給食の食べかけのパンを千切って、橋の下にポンポンと投げ込んでいました。ゆう子ちゃんは言いました。「パン嫌いなの」凄い発想だと思いました。僕も給食の食べかけのパンを千切って、橋の下にポンポンと投げ込みました。ゆう子ちゃんは自分の発想に照れる様に、「前からやってるの」と言いました。
次の日、僕とゆう子ちゃんは、橋の横の土手に座って、ある鯉は野鯉、あの鯉は錦鯉、だとか、見れば分かる事を言い合って、パンを千切ってはポンポンと橋の下に投げ込んでいました。
次の日、真似をする奴が現われました。台風が来ると興奮してブーンブーンと鼻を鳴らしながら庭を駆けずり回るブーちゃんと言う名のウサギと、ミーちゃんと言う名の猫を飼ってる野屋君です。三人はポンポンとパンを投げ込み、それだけじゃ飽き足らずに、家からパンを持ち寄り、パンを千切っては投げ、千切っては投げ、鯉が跳ねた、跳ねてないとか言って、盛り上がりました。小山さんは家が遠いので、家からパンを持ち寄る事が出来ずに、少し寂しそうでした。
また次の日には、大輔という男らしい名前を持つ犬を飼ってるケイちゃんが加わりましたが、飽きっぽいのですく飽きました。僕と野屋君は大盛り上がりで、鯉が増えた、増えてないとか言いながら、パンをポンポンと投げ込みました。小山さんは自分のパンを投げ終わると、いつもボンヤリと鯉を眺めていました。
また次の日には、ボブの頭にバカでかい石をヒットさせたタモツが加わって、自分のパンをビシバシッと投げ終わると、画期的なアイデアを出しました。「パン屋のオヤジにパンの耳を貰おう!」野屋君は、「イイねソレ。イイ感じ」と言って、二人はアッと言う間にチャリンコに乗って去って行きました。僕は自転車に上手く乗れない様なガキでしたので、ゆう子ちゃんと一緒にボンヤリと橋の上に立っていました。「もう帰るね」ゆう子ちゃんはそう言って歩いて行きました。
次の日、タモツと僕と野屋君は、学校の帰りにパン屋に寄りました。すると、パン屋のオヤジは、パンの耳をビニール袋に入れて待ち構えていました。
すると、クラス中の噂になり、やがて、学校中の噂になり、みんなが僕等の真似をしだしました。パン屋には学校帰りの小学生が列を組み、パンの耳には十円かそこらの値段がつけられました。鯉は増えに増え、橋には人々が集いました。小学生から知らない人まで。オッサン、老人、オバさん、恋人。中には本物の鯉の餌を持って現われるババァもいましたが、「あらぁ、食べないわねぇ?、どうしてかしら?」と、言っていました。僕等はうふふ、と勝ち誇りました。もうここの橋だけではなく、ずっと向こうの橋でも、全く同じ事が起こっているのです。僕はもう、すっかりリーダー気分のヒーローでした。皆が、「ほら、あの子が鯉に餌をやりだしたのよ」「すごいねー」などと、僕の噂をしていました。それにしても、小山、最近来ないなー・・
そんなある日の、暗くて、赤紫色の夕方に、ゴゴゴーと音がしました。外に出てみると、橋の上には近所の人が集まって、川を見下ろしていました。野屋君もいました。ケイちゃんもいました。「ジュンちゃん、ちょっと見てみろよ」とケイちゃんは言いました。近所のオバさんが怒っていました。「ヒドイわねー、あんまりよー」川を見ると、鯉が次々に流されていました。橋の横の土手にある機械が、聞いた事のない轟音を轟かせて動いていました。川の水は真っ茶色のドロ水と、洗剤の泡に溢れていました。水量はいつもの三倍程で、川の流れの強さは異常でした。「ダムよ、ダム!、開けたのよ、勝手よね、勝手!」川の流れに負けまいと、必死になって抵抗して泳いでいる鯉が、ビシッと跳ね上がって流されるたびに、溜め息まじりの声が上がりました。「あーあ・・」
暫らく川の流れを見つめていました。すると、隣にいた眼鏡のオバさんが、僕を見て、「この事、作文に書いたら?」と言いました。僕は頭の中が真っ白になり、オバさんを見つめました。「・・・」僕と野屋君とケイちゃんは、「すげー、見ろよ、この流れ」「全く冗談じゃねーよな」「ヒドイよな」などと、笑って、走って、家に帰りました。夕日は赤かったのに、空は真っ暗な紫色でした。僕は家に駆け込み、玄関のドアを閉め、靴を脱ぎ捨て、トイレの前で泣きじゃくりました。・・あの眼鏡のババアだけは許せない、と心の中で怒り狂いながら・・
次の日の朝、川の水はほとんど干上がっていて、何匹もの鯉が仰向けになって、真っ白い腹を露にして死んでいました。チビッコは、鯉を喰いばもうとしているカラスに向かって、キャーキャー言いながら、石を投げつけていました。水深十センチ程の川の流れを、逆方向に泳いでいき、どこかに突き進もうとしている野鯉が一匹だけいて、皆で応援していましたが、僕は、それを横目で見て、歩いていきました。
そんなある日の日曜日、僕は野屋君ちに遊びに行こうと思って歩いていました。すると、川へと下りる土手に誰かいます。見ると、草むらの向こうに見える、あの小太りの女の子は、小山ゆう子ではありませんか?。土手に下りてみると、小山さんは言いました。「ここは深くなってるからまだいるの」「あんなにたくさんの鯉がどこいったのかと思ったら、ここにいたのか」そこは川と言うより、沼の様な感じでしたが、鯉は確かにいました。以前よりもフテブテしく、逞しくなったように見える鯉、群れをなして泳いでいます。僕はさっそく野屋君ちに駆け込み、野屋君に報告をし、三人で相談をしました。僕等はその場所を三人の秘密の場所にする事にしました。
そして、こっそりと、三日程、パン屑をやり続けました、が、鯉は全く食べません。「・・ここには餌が一杯あるんだよ」「・・うん」小山さんは鯉が泳いでいるのをジッと見つめていました。「・・あ」小山が指差した方向を見ると、白い、狐の様なものが、サッと草むらの中に消えました。「キツネ?」「タヌキ?」「オコジョ?」
「オコジョ?、何それ?」「北国にいるヤツだよ」「ここ、神奈川だよ?」オコジョは昨日たまたま、野屋君ちの動物図鑑で発見した動物でした。「オコジョだよ!、オコジョ!」僕と野屋君は、オコジョを捕まえようとして、草むらの中に駆け込みました。いる訳もないのに・・。ゆう子ちゃんは「オコジョ」と言う名前がツボに入ったらしく、いつまでも、笑っていました。
「屑」用済みで役に立たなくなったもの。必要な(いい)ところを取り除いた残り。価値のないもの。「パン−」「−川」「あいつは人間の−だ」
「くず」葉のつけ根に、赤紫色の花が、ふさのようになって、咲く
あの夕焼けが、くずの花なら、あの白いものは?
「くずの裏風」くずの葉を吹き返す風。裏が、白みがかって返るのに、興をもって歌によまれる。
「オコジョ」ツボに入ると感じる、必然の(善い)もの。「あいつは人間の−だ」
この話は一度だけ新宿二丁目の新宿公園で話した事がある。僕はベロンベロンに酔っ払っていて、隣にいた女の子も可愛く、ブランコもいい感じに揺れていて、夏の夜で、気持ち良く、ラブホに行く様な気も大してしなかったので、公園にいる皆に聞こえるように大声で話した。今ここに書いたのは、雨の音がうるさく、眠れなかったからだ。あの時と同じ午前3時に書いたけど、あの時口で話した程には上手く書けなかったかも知れない。まぁ、作文なんて、そんなもんだネ。
![]() (2002.3.19)
(2002.3.19)
| いそのカツオをブッ殺せ! Copyright(C) 2002 矢萩純一 題字: 矢萩純一 デザイン: おぬま ゆういち 発行: O's Page編集部 |